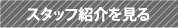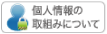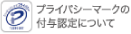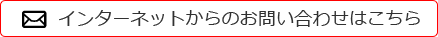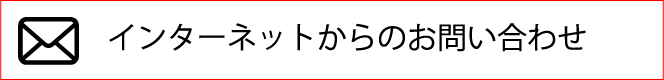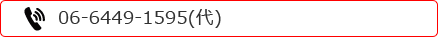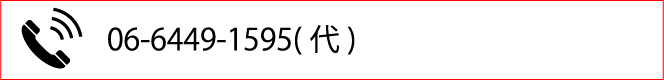書店に行けば、「仮説思考」(内田和成著)という本があります。著者は、「仮説思考」の効用を以下のように整理してくれています。
- 仕事をこなすスピードが速くなる(意思決定が速くなる)
- 仕事の質が高くなる(意思決定の質が高くなる)
- 仮説思考の特徴である「全体像から入って必要な部分のみ細部にこだわる行為」の積み重ねで、物事の全体像をつかむ力が向上する
何やらこれは、調査の設計や分析段階においても大切そうですね。
2.調査と仮説
さて、調査には大きく3種類があります。①実態把握型調査、②仮説検証型調査、③仮説発見型調査です。以前の連載では、③仮説発見型調査に関連する話題を書かせていただきましたが、今回は②仮説検証型調査に関連する話題と言うことになります。
3.人間の調査仮説の活用の発達段階
「仮説検証型調査」には、もちろん前提として検証すべき「仮説」があるはずです。そして、調査企画の段階で、その仮説があっているかどうかを確認する調査項目を設定します。そして、定量調査、定性調査を実施して調査データ(FACT)を取りに行きます。
でも、意外と「仮説検証」という思考プロセスは難しいなぁ、と感じています。以下、私が20代だったころから感じてきたこと、体験してきたことを振り返ってみたいと思います。
〇第一段階
20代後半だったと思います。仮説検証型のGIをバックルームで見ている最中、もしくは調査のレポート作成時に起こった現象は、「仮説」を肯定しようとする行為でした。
仮説に当てはまる情報のみをピックアップして「やはり仮説通りだった」と結論付けようとしてしまう。悪意があるわけではありません。「仮説」を持つとそれを肯定する情報のみが自然と脳の中に蓄積されてしまうのです。
仮説に当てはまる情報のみをピックアップして「やはり仮説通りだった」と結論付けようとしてしまう。悪意があるわけではありません。「仮説」を持つとそれを肯定する情報のみが自然と脳の中に蓄積されてしまうのです。
〇第二段階
次に訪れた段階は、調査結果では「仮説」を肯定するデータもあるが、否定するデータもあるという場面に遭遇し、迷いたじろぐ段階。どうしようかと悩んでしまいます。「仮説を肯定するところだけを使ってまとめてしまおうか。そうすれば迷わなくて済む」という悪魔のささやきとのせめぎ合い。
この時に求められるのは、「仮説」を一旦捨てて、再度データを見て「仮説」を再構築することが必要ですね。そういった姿勢で、再度データを見てみる。「仮説」を捨てる勇気を身に付ける段階だと思います。
この時に求められるのは、「仮説」を一旦捨てて、再度データを見て「仮説」を再構築することが必要ですね。そういった姿勢で、再度データを見てみる。「仮説」を捨てる勇気を身に付ける段階だと思います。
〇第三段階
「仮説」を持って調査設計をするのですが、GIなどの実査の段階では、既に「仮説」の枠から脳が解放され、自由な姿勢でFACTを眺めることを楽しむ段階。はなから「仮説は仮説。的確な調査項目を洗い出すために必要なものだが、実査が始まってしまえば仮説は一旦忘れてもいい」という感覚ですかね。
若いころ、これらの段階を登って行くのに苦悩した覚えがあります。私の様な凡人は、常に意識しないとできないことかもしれません。
でも、こうやって見てくると、「仮説検証型調査」とは言いますが、実はその実査段階、分析段階において、新たな仮説を発見する「仮説発見型調査」でもあると言えるのではないかと思えてきます。
4.弊社が「仮説構築」に関わる2つのパターン
ちょっと話は変わりますが、弊社が「調査仮説」に関わるパターンとしては、以下の2つのパターンがあります。
①お客さまの頭の中にある仮説をきちんと整理して理解した上で検証する
お客さまに丁寧にヒアリングをして、お客さまが抱える「マーケティング課題」、そのマーケティング課題の原因となっている「課題仮説」、それに対してどういう施策が考えるのかという「戦略仮説」、そして今回の調査で検証すべき「調査課題」の4つのレイヤーで整理するパターンです。
これは、お客さまが立てた「仮説」を検証することをメインの目的とし、調査設計の段階で新たな「仮説」は求めていない場合に適応されます。
ここで弊社に求められている能力は、お客さまに寄り添って思いを共有し、マーケティングプロセスに当てはめて、きちんと整理できることだと認識しています。
これは、お客さまが立てた「仮説」を検証することをメインの目的とし、調査設計の段階で新たな「仮説」は求めていない場合に適応されます。
ここで弊社に求められている能力は、お客さまに寄り添って思いを共有し、マーケティングプロセスに当てはめて、きちんと整理できることだと認識しています。
②クリエイティブな仮説をお客さんと一緒に創造し検証する
もう一つは、「仮説」をお客さまと弊社で共に考えて創造するパターン。お客さまが、ご自身で考えられた仮説の枠を超えて新たな気付きを(潜在的にでも)求められている場合に適応されます。
ここで弊社に必要な能力は、弊社なりのクリエイティビティのある仮説構築力です。
ここで弊社に必要な能力は、弊社なりのクリエイティビティのある仮説構築力です。
いずれのパターンでも、弊社は価値をご提供したいと思っております。すみません、なんか最後は営業チックになってしまいました。お許しください。。。
(立田)