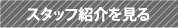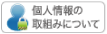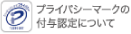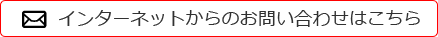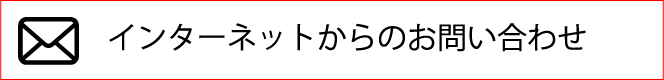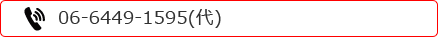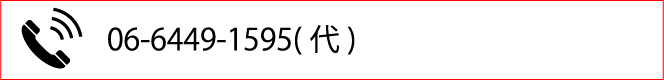人生の折り返し地点を超えて、終盤に向かっている年齢がそうさせるのか、最近の社会不安がそうさせるのか、マーケティング・リサーチに携わる中で、「社会的価値」ということを意識するようになってきました。
(とは言え、「何か行動を起こせているか」と問われれば、お恥ずかしながら何もできていないのですが…)
■マーケティングとは、生活者の幸せ・満足といった価値を創造すること
コトラー先生によると、マーケティングとは「価値を創造し、提供し、他の人々と交換することを通じて、個人や組織が必要(ニーズ)とし欲求(ウォンツ)を満たすことを意図する社会的、経営的活動である」と定義されています。一方で、マーケティングの中身は変化しているとし、その変化を次のようにまとめています。
「マーケティング1.0:製品中心主義(Mind)」「マーケティング2.0:消費者志向(Heart)」「マーケティング3.0:価値主導(Spirit)」「マーケティング4.0:自己実現(Self-Actualization)」。
ただ、これらは、あくまで「生活者個人に対する価値創造」と捉えられます。
■ソーシャル・マーケティングという概念
「ソーシャル・マーケティング」というコトバがあります。
コトラー先生は従来のマーケティングの技法を企業だけでなく、政府、博物館といった一般の非営利組織にも応用、拡張していこうとするものであるのに対し、W.レイザーが提唱した「ソーシャル・マーケティング」は、これまでのマーケティング行動に社会対応が欠如していたという反省のもとに、評価判定基準に社会的利益や価値をおこそうとする考え方のようです。4Pを中核とする伝統的なマーケティングに欠けていた社会的責任や社会倫理といった社会的視点を導入したものですね。
■深刻化する社会問題
日本における少子高齢化、人口減少が社会に与える影響はとてつもなく大きいです。
労働力不足による経済規模の縮小、国の財政不安(年金・医療・介護など福祉諸制度の維持が困難に)、地方都市の消滅(2040年には地方自治体の半数が消滅の恐れに晒されているとの予測が)、無縁社会(コミュニティの希薄化)などが思い浮かびます。加えて、自然との共生問題、更には政治の右傾化なども、私にとっては大きな不安材料です。
日本が直面しているこのような社会問題は、次世代に大きな傷を残すことになることは間違いないでしょう。
マーケティング、もしくはマーケティング・リサーチの仕事を通して、少しでもこれらの課題に対処していくことはできないものでしょうか。
■「共通価値(CSV)の創造」という概念 ※Creating Shared Value
マイケル・E・ポーター先生が提唱している概念に「共通価値(CSV)の創造」あります。「顧客のニーズに対応するだけでは不十分だ」という主張で、共通価値(Shared Values)とは、経済的価値を創造しながら、社会的ニーズに対応することで社会的価値も創造するというアプローチです。
CSR(Corporate Social
Responsibility)も有名ですが、社会貢献活動(フィランソロピー)や慈善活動的色彩が強く、企業の事業活動とは直接的な結びつきが希薄と捉えられがちです。
対して、CSVは経営戦略の一つとして、本業に即した形で社会的課題を解決する取組みを行っていくという考え方です。
ネスレの「ネスプレッソ」(アフリカ・中南米のコーヒー豆栽培農家の経営・技術支援、環境負荷の軽減、自社にとっては上質豆の安定供給)、明治の「チョコレート」(ネスレ同様の価値)、パナソニックの「GOPAN(ゴパン)」(米需要の拡大)などが事例として挙げられることが多いようですね。
「本業で儲けながら、直接、社会的な価値も生み出せ」ということなのでしょう。
■何ができるか
リサーチ会社である弊社が、経営戦略・事業戦略のお手伝いをすることはなく、ネスレの事例のようなバリューチェーンの構築といったことに携わることはありませんが(今のことろ…)、商品・サービスコンセプト作りに関わらせていただくことはあります。
コンセプトは、①ターゲット・インサイト、②機能的価値、③その根拠となる商品属性、④情緒的価値などで記述・定義されることが多いと思いますが、ここに「社会的価値」という項目を必須とする、という考え方はいかがでしょうか。
コンセプト作りの段階で、先に述べた社会問題の解決に、少しでも、間接的にでも、何かしら寄与できる要素を埋め込む、そういったことを日々考えることが大事なのかもしれません。
小さな努力の積み上げが求められているのではないでしょうか。
(立田)