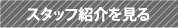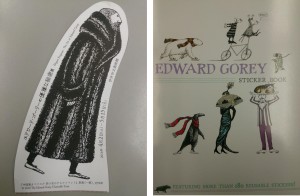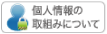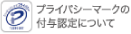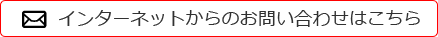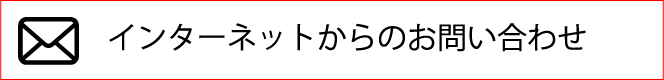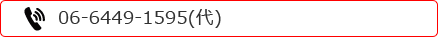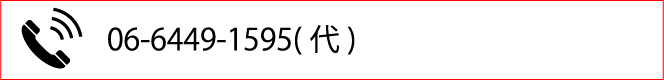大阪市のみならず、政治・行政で今大きなトピックと言えば「大阪都構想」。大阪市民である私にとっては自分の生活基盤に関わることでもあり、「ここはぜひ賛成派、反対派それぞれの言い分を聞かねば」と、まずは大阪市主催の「住民説明会」に出向いたところ、会場2時間前の時点で「満員札止め」となっており入場できず。逆に一般的な生活者の関心が高まってきたことの一端を見ました。
仕方なくネット上で公開されている説明会やTV番組での討論・説明などを一通り見ていって、思ったこと。互いの主張・政策についての是非はここでは述べませんが、一つ確実なのは維新の会、というか橋下市長のプレゼン能力の高さ。中身はともかく、この点においては反対派の貧弱さが目につくこと。。
■プレゼンはコミュニケーション能力が試される場
弊社はリサーチ会社ですから、リサーチのアウトプットを報告会という場でプレゼンすることがあります。また弊社のリサーチ商品である座談会やデプスインタ
ビュー等の進行(モデレーティング)も、対象者とのコミュニケーションの場となります。もちろん調査報告会はリサーチ結果を「伝える」場、インタビューは相手の気持ちを「聴き出す」場であり、それぞれ情報の流れは違ってきますが、相互のコミュニケーション意識が高まっていないといい結果に繋がらないことは自明の理です。それらの場を少なからず経験して感じているのは、「話し方や発声の仕方」が潤滑なコミュニケーションに重要か、という事です。
■聴覚・視覚のサポートがないと、伝えたい情報の1割も伝わらない
もちろんプレゼンというのは報告する、もしくは提案する内容があり、まずはその質が一番大事ですし、その内容を的確に伝えるような資料の作り方も求められます。ただ、せっかく優れた提案も、工夫を凝らした資料も、その内容を伝える「話し方(声、トーン)」次第で、活かされもすれば損なうこともあります。
「メラビンの法則」という心理学のコトバがあります。その中で対面によるコミュニケーションでは、話し手が受け手に与える影響には「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の3つの要素があると定義されています。そして対面して話すコミュニケーションにおいて、どの要素がどの程度の影響力をもつかという実験を行ったところ、
・言語情報(言葉そのものの意味や内容):7%
・聴覚情報(声のトーンや話す速さ、大きさ、口調等):38%
・視覚情報(見た目、表情、態度、ジェスチャー):55%
という結果が導き出されたということです。
とかく何かを伝えようとするときに、どうしても「伝える内容」の精査に時間も気持ちもとらわれがちですが、実際に受け手に与える影響は話の内容ばかりではない、ということを、この法則は表しています。
例えば欧米各国のリーダーの演説を見ると明らかで、ステートメントの内容もさることながら、声色やトーン、ジェスチャーなどに、実に気を使っていることが見て取れます。もちろんこれらは彼らの資質だけではなく、プレゼン専門のトレーナーが背後にいるからですが。ことほど左様に、決められた時間の中で判断して
もらうプレゼンの場では、もしかすると伝える内容と同レベルで、「聴覚」要素を気にする必要があると思います。
■「あうんの呼吸」は、ビジネスシーンでは通用しない
各国リーダーの演説の立居振る舞いについて述べましたが、従来の日本国の首相の演説はこの点が大きく遅れていました。最近の安陪首相の話し方を見てると、明らかにプレゼンのトレーニングを受けている様子が見られますが、つい最近までの首相のプレゼン能力の低さは明らかでした。
これは日本という国特有ものなのかもしれません。欧米とは違い(ほぼ)単一民族であり、周りを海に囲まれているという地理的環境から、日本人の中には10は
語らずとも相手の言いたいことが伝わる、もしくは相手の気持ちを汲もうとする気持ちが、無意識的に存在しています。これは日本人の美徳でもあり、それはそ
れで誇るべきことなのですが、ことビジネスシーンにおいてはネガティブになります。
自分の主張を相手に確実に効果的に伝えるには、「内容」「声」「態度」の三位一体が必要であるということが
今回の都構想議論の素材を見聞きする中で、より実感した次第です。
もちろんプレゼンテーションとアジテーションは違うわけで、一見すると説得力があっても変に扇動されるのではなく、その内容を理解したうえで、冷静に情報内容を咀嚼する能力が、情報の受け手側にも求められるわけですね。
(山本)